みなさんこんにちは、キャリア迷子管理人のさいとぅーです。
キャリア迷子でインタビューをすると、主に転職周りの話にフォーカスすることが多くなりますが、単純にほかの会社の人とか、ほかの職種の人ってどんな仕事してるんだろうって気になること結構ありますよね。
というわけで、改めて「お仕事インタビュー」というカテゴリを切り分けて、仕事の方に着目してインタビュー記事を書いてみることにしました。
 さいとぅー
さいとぅーというわけで、転職時の職業訓練校とかにもある関係で、デザイナーに興味がある未経験の人も多いから、デザイナーについて色々聞いていい?
私で良ければいいよ!あ、あと会社辞めて独立することにしたわ!



インタビューをお願いした時点ではまだ会社員だったはずなのに。
何この急展開
まず時系列で聞きたいんだけど、デザイナーになろうと思った経緯は?
「前置きとして言っておくけど、私みたいなケースはほとんどないと思うんだよね。なんでかっていうと、私、中学生で職業を決めたのよ。絵を描いてる友達がいて、それがきっかけで『好きなこととか得意なことを仕事にするにはどうすればいいんだろう』って考えるようになったの。
その頃ちょうど、グラフィックデザイナーっていう職業が世間で知られ始めてた時期だったのよね。あと、1970年の大阪万博やいろんなイベントも相まって『デザイナー』っていう職業がようやく認知され始めたっていうのも大きかったと思う。
そんな感じで、『絵を描くことを仕事にできるんだ!』って親と話して知ったんだけど、勉強ができないと話にならないから進学校に進んだわけ。でも、高校1年生の時点で『私はデザイナーになる!』って決めてたから、芸大に行くってことはわかってたの。で、そのためにはデッサンのスキルが必要だなと思って、デッサンのスクールに通ってたんだよね。」
大学はどうやって決めたの?
「これがちょっと変わってるんだけど、高校が神戸だったから、就職はおそらく大阪だろうなって思ったのよね。それで、『じゃあ大学は京都に行こう!』って。場所的に、いろんなところを経験したいなって思ったのもあるし、その時は京都の大学がレベル高いイメージがあったのも理由のひとつ。あと、京都には美大が結構たくさんあるってのも大きかった。
それで、公立の芸大と私立2校に出願して、合格した大学に進学したの。」



他にも大学選びの理由とかある?
そうだね、京都の大学って美術分野が進んでるし、環境としても学びやすいと思ったの。やっぱりそういうことを総合的に考えて選んだ感じ。
美大合格って普通の高校で勉強してるだけじゃ無理そうね
「そうなのよ。公立の大学や一般入試だと、美術の練習に加えて加えてセンター試験の成績も必要なんだよね。だから、まずその水準を超えないと受験資格すらないって感じ。偏差値的には、関西だと関関同立くらいかな。東京で言うとMARCHと日東駒専の間くらいのレベルじゃないかな。」
美大って通ってる間も大変そうだね?
「うん、大変だったよ。課題の量が多いのが一番しんどかった。1年生のときは週4日くらい講義があって、全体で25コマくらいのうち半分が制作系の授業だったかな。で、その制作の課題が3週間ごとに仕上げるペースで出されるんだけど、授業中に終わらなかったら、授業以外の時間を使ってどうにかするしかないの。
それに加えて私は図書館司書の資格も取ろうとしてたから、土曜日も学校に行ってたんだよね。」



私には無理だ。。。
なんで図書館司書の資格を取ろうと思ったの?
「本が好きだったのもあるんだけど、中学のときにトライアルウィークっていう職業体験があったのね。それで図書館で働く体験をしたら、めちゃくちゃ楽しかったの!それで、司書の資格が必要だって聞いて、『じゃあ取ろう』って思ったの。お金もかからなかったしね。でも勉強する時間は増えたけど(笑)」



その司書の資格って、今まで生きたことある?
資格として直接使ったことはないかな。でも、本屋さんで本を見るときの目線とか、役に立ったことはあるよ。あと、一社目で模試関係のデザインを作ってる会社に入ったんだけど、勉強系の知識が多少あったから内容を理解しやすくて、司書の過程を取っておいて本当に良かったなって思った
芸大の課題の感じって、なんだかブラックっぽくなりそう。
「まあ、確かにね(笑)。私はそれに加えてバイトもしてたから、ほんと時間がなかったよ。制作の授業で課題を期限までに提出しないと単位がもらえないんだけど、間に合わない人も一定数いたのね。1週間遅れて提出する人もいたし、それでクオリティが高いものを出して評価される人もいたけど。
それが結構気に食わなくてさ。『出せば単位は取れる』みたいなのもあったけど、私は課題の納期を守ることをすごく意識してた。だから、この時に『時間内にきちんと仕上げる人になろう』って決めたの。」



ちなみに納期を守れない人って、その後どうなったの?
あくまで私の周りはだけど、そういう人たちは就職がうまくいかなかった印象かな。新卒で就職しても半年以内に辞めちゃう人が多かったね。先生たちもそこまで厳しく言わないんだけど、『締め切りを守らないと社会では通用しないよ』ってやんわり言ってくれてたんだよね。でも、それが伝わらない人も多かったみたい。



単位とか卒業どうなるのか的な意味で聞いたつもりだったんだけど、より辛い現実が。。。
一社目を決めた理由は?
「一社目は通信教育や問題集、模試とか、私が学生時代から馴染みがあった媒体を扱ってる会社だったの。進学校出身だったから、それに親しみがあって、それに携われるならいいなって思ったのが理由の一つだね。
あと、私が就職活動してたのはリーマンショックの4年後くらいで、就職氷河期だったんだよね。特に新卒でデザイナー職ってなると今よりさらに就職口が少なかった。企業も新卒を育てようっていう文化があんまりなくて、即戦力を求める感じだったのね。そんな中で、なんとかその会社に入れたって感じ。」



働いてみてどうだった?
正直、今で言うOJT(On-the-Job Training)なんて皆無の世界だったよ。『そこにある資料読んどいて』とか、『見て学んで』みたいな感じ。覚悟してたから特に悲観したわけじゃないけど、現実はこんなもんかーって思った。キラキラした職場を想像してた人は辞めていったけどね。
一番驚いたのは、職場の自分の席でタバコ吸ってる人がいたこと!
『燃えますけどカンプ…』って思った(笑)



今から10年前でもそんな感じの働き方残ってたんだwwwww
じゃあ、デザイナーとして具体的にどんな仕事をしてたの?
「一社目では、アシスタントデザイナーみたいな職種はなかったから、最初から先輩たちと同じ仕事をしてた。私が所属してた会社は、1つの案件を3人1組のチームで回すスタイルだったのね。チームが2つあって、それぞれに新卒が1人ずつ配属されてた。同期がいたのは心強かったかな。
同期がいたチームは、某大手教育会社のDMをひたすらやってるチームだった。私は、問題集の表紙デザインとか、DMの補助をやったり、広告代理店から受注した案件とか、印刷会社の案件も担当してた。あとは、高校の先生向けの取材雑誌を年に13本作ってたよ。」



なんか、まっきーのチームのほうが負担が重そうに聞こえる。
まあ、そうかも(笑)。もう一つのチームの人は20年その会社にいて、その教育系企業の人から指名されるくらい信頼関係があったからね。特に、DM制作に特化したデザインセンスを持ってる人がいて、その人がバリバリやってた。DMってペライチじゃなくて、冊子やチラシが色々一式で入ってるから、一つのチームで全部まとめて走らせないと大変だったみたい。
新規案件が来た時って、どんな流れで進むの?
「広告代理店からの案件を例にすると、最初にメールで『こういうのがあるんですけど、お仕事可能ですか?』って連絡が来るのね。で、『可能です』って返したら、打ち合わせが発生する感じ。そこでヒアリングをして詳細を詰めるのが流れだったかな。」
そのヒアリングって誰がやるの?
「基本はリーダーとか担当デザイナーがやるんだけど、私は『外に出たい!』ってずっと言ってたから、リーダーと一緒にヒアリングに行かせてもらってた。直接その場で話を聞かないと趣旨がズレたり、やり直しが増えるのが嫌だったのよね。業務量がパンパンだったから、なるべく最短で終わらせたいっていう気持ちもあったかな。」
ヒアリングの後はどうなるの?
「その場で大まかな方向性と納期を決めて、あとはメールや電話でやり取りするの。で、最後に納品って流れなんだけど、ここでややこしいのが、『納品』と『入稿』っていう言葉の意味が会社によって違うのよ。
例えば、クライアントが『納品』って言う時に、完成品の現物を指してる場合もあれば、デザインデータだけでOKな場合もある。こういう言葉の違いでミスが起きやすいから、毎回『納品』と『入稿』をどう使い分けてるのか確認してたね。」
じゃあ、実際のデザイン部分についても聞かせて!



まっきーに聞くと「あとは作るんだよ!!!」で終わりそうだから、もうちょっと詳しく教えてほしい
「確かに(笑)。媒体によって全然変わるんだけど、例えばチラシやパンフレットのデザインを担当する場合で話すね。基本的には原稿とか内容はクライアントからもらうのよ。でも、ほとんどの場合、絵がない状態でスタートすることが多いの。つまり、テキストだけがあって、それに対してビジュアルを作っていく感じ。
最初にクライアントと打ち合わせして、ざっくりとした方向性を聞くのよ。『このターゲットに響くものにしたい』とか、『春っぽい感じにしてほしい』みたいなことを言われるから、それを掘り下げてラフ案をその場で手書きで書くこともあったね。それを見せてOKもらったら、具体的なデザインを進めるって流れ。」
デザインのツールって何を使ってたの?
「当時はイラレ(Illustrator)とフォトショ(Photoshop)だけで全部やってたね。原稿はWordでもらってたから、それで十分だったかな。今みたいにいろんなツールがある時代じゃなかったから、シンプルな環境でやってたよ。」
チラシをデザインする時って、統一感が難しそうだけど何を意識してるの?
「そうだね、例えば野球のチラシを作る時は、まずターゲットを想定するのよ。その人たちが『野球』って聞いたらどんなイメージを持つかっていうテイストを探す。で、それを作り出す前に、世の中にあるデザインをとにかくたくさん見るの。最低でも50以上、100近く見てたかな。ザッピングする時間を1〜2時間くらい作って、資料を集めるんだよね。」
その資料ってどうやって集めてたの?
「今みたいにPinterestみたいなWebサービスがなかったから、会社に置いてあるデザイン書をひたすらめくってたね。あと、雑誌を探して、関連するページに栞を挟んで集める作業もしてた。当時の会社では毎月5冊くらいデザイン書を買ってたから、それがベースになってたかな。インハウスのデザイン部門だと、過去の制作物を参考にすることが多いと思うけど、制作会社だとそういう外部資料に頼ることが多かったね。」
過去の制作物も参考にしてた?
「うん、もちろん。自社で作ったものを全部見て、『これ誰が作ったんですか?』って聞くと教えてくれることが多かったの。それで、作った人に直接話を聞きに行ったりしてたね。基本的には『見といて』って言われて放置されることがほとんどだったけど、そういう文化の中で自分で学ぶのが普通って感じだった。」



それって職人文化っぽいね。教えてもらえないと不満に思う人もいそう。
そうそう、職人文化そのものだよね。正直、上の人に『教えてほしい』って言っても、あんまり通じないのよ。見て盗むのが普通だから。でも、後から考えると、『見といて』って言ってもらえるだけでもありがたいなって思うようになったよ。その一言すらない環境も多いからね。
逆に、過去の制作物が蓄積されてない会社もあるのよ。そういうところだと、新人が何を学べばいいのかわからなくて困るんだよね。だから、ちゃんとした資料がある環境ってすごく大事だと思う。



決められた形のない製作系の仕事は、決められたやり方を知るより、調べ方とか参考資料の探し方の方が学ぶべき事なのかもしれないわね。
そういう資料がない場合、どうやって参考にするの?
「ネットのデザインサイトを使うこともあるけど、私は書籍推しだね。本だとクオリティが担保されてるから、アイデアの引き出しを増やすには最高なんだよね。ネット上のものは、クオリティにばらつきがあるから最終イメージ作りには向かないかな。」
紙媒体が中心だった話は聞けたけど、その後はどうだった?
「次の会社も制作会社で、紙だけじゃなくてWebの制作も入ってきた感じかな。範囲が広がったって感じ。」
Webのデザインに初めて挑戦した時ってどうだった?
「実は一社目で無茶振りされて、自社サイトのデザインとコーディングをやらされたことがあったの(笑)。だから、次の会社でWebの仕事を受けた時には、そんなに抵抗なかったんだよね。」
その無茶振りされた時の話、詳しく教えて!
「それがね、当時のお客さんが情報漏洩を起こした時で、半年くらい仕事がなくなっちゃったのよ。その時、社長が『今後Webの案件も増えるかもしれないから、AdobeのDreamweaverをみんなで習いに行こう』って言い出して、みんなで勉強しに行ったの。
実は大学時代に少し触ったことがあったから、『せっかくだし何か作りたいね』って話になって、結果的に私が自社サイトを作ることになったの。その時にコーディングもやったから、後々コーダーと組む時に、言いたいことが理解できてすごくやりやすかったよ。」
デザイナーがコーディングを覚えるべきか、よく議論されるけどどう思う?
「コーディングができなくてもいいけど、勉強はしたほうがいいと思うね。自分でコードを書けなくても、『何をするとどうなるのか』を理解することが大事。デザイナーも、コーダーにも『デザインの意図を理解してほしい』って思うから、両方に歩み寄りは必要かな。デザイナーだからって、コーディングの世界にまったく触れないのは甘えだと思うよ。」
じゃあ、次の会社でWebの仕事を受けた時の流れを教えて。
「この会社はちょっと変わったフローだったから、一般的じゃないってことは先に伝えておくね。社長がクライアントからWeb案件を受注して、まず社長自身が手書きでワイヤーフレームを引いてたの。
それをもとにコーダーが先にコーディングを始めるって流れだった。なんでかっていうと、案件のほとんどが印刷物のカタログをWebに転用するものだったのよ。カタログのデザインがすでにあるから、コーダーはそれを見てコーディングを進められるって感じ。私はその後、必要な画像やパーツを抽出して組み合わせたり、最終監修をする役割だった。」
それって逆の流れみたいだね。一般的な流れはどうなの?
「そうだね、一般的なWeb制作の流れは三社目でやったやり方が近いと思うよ。最初にクライアントからヒアリングした内容をもとに、手書きや写真を切り貼りしたようなラフを作るの。それを情報として画面上に落とし込んで、ワイヤーフレームを作成するんだよね。
そのワイヤーがクライアントからOKをもらったら、次にデザインを進めるの。ベンチマーク先や競合情報も事前に聞いておくから、それを踏まえながらデザインを考える。もちろん、コーディングで実現可能な範囲を考慮しながら作るのが良いね。」
その後の流れは?
「デザインが完成したら、PDFとかカンプでクライアントに提出して確認してもらう。それからコーディングに進んで、テストサイトを作成、最終的に公開って流れだね。」
Web制作で困ることってある?
「うーん、やっぱりコミュニケーションかな。紙媒体よりも関わる人数が多くなるから、『誰の意見を優先するか』とか『どう見せるのが正解か』って迷うことが多いんだよね。それに、お客さんがWebの仕組みを理解してないこともよくあって、ディレクターがその説明に苦労してるのを何度も見たよ。」
デザイン自体での苦労は?
「Webデザインって、時代の流れで評価がすぐに変わっちゃうのが大変だよね。1年前にすごく良いって言われたデザインが、今ではもう古いって言われることもある。グラフィックデザインだと一度評価されたら実績として残るけど、Webは情報が早い分、走り続けなきゃいけない感じがする。そこが辛いところかな。」
デザイナーとしての経験を踏まえて、デザイナー希望の人に何か伝えたいことはある?
「デザイナーって、作ったものに対してフィードバックをもらうのは当たり前なんだけど、たまにそのフィードバックが性格否定みたいになっちゃうことがあるのよね(笑)。だから、その辺の覚悟はしておいたほうがいいと思う。
あと、デザイナーってキラキラした職業だと思われがちだけど、現実は全然違う。憧れだけで入るとギャップが大きいから、本当にやりたいことがある人だけが入るべき職業だと思う。」
最後に、デザイナーを目指す人へのアドバイスをお願いします。
「勉強したくないけど絵が好きって理由で美大や芸大を目指す人も多いけど、結局、デザインって勉強が必要不可欠なんだよね。これは特定の職種だけじゃなく、全人類に共通する話だと思うけど。だから、甘い考えで入ってくると厳しい世界だよってことは覚えておいてほしい。
それと、デザインを評価するのは必ずしもデザイナーじゃないから、そのギャップを埋めるのも大事。お客様の抽象的なリクエストを具体的な形に落とし込む能力が必要なんだよね。クライアントとちゃんとコミュニケーションを取ることが、最終的には一番大事なんじゃないかな。」
こんなんで良かったかしら



デザイナーは特にキラキラ系の広告とかインタビュー記事いっぱいあるので、生々しいやつ頼むよってお願いしたオーダー通りだね!
というわけで、インタビューは以上です。
『お仕事インタビュー』では、他にもいろいろな業界や職種の人の話を聞いていきたいと思っています。
今回みたいに突っ込んで色々聞かせてくれる人は教えてくださいね!
こういう人の話を聞きたい!という要望もコメント欄とかで色々意見貰えると嬉しいです!
あと、まっきー独立したらしいので、デザイン系のお仕事のご依頼があったら教えてくださいね!
仕事にこだわりがあってコミュニケーション取れるデザイナーなのでドンドン仕事振ってあげてください!
紹介してほしい方は私にご連絡してくれてもだいじょぶです!
ちなみにキャリア迷子コミュニティのロゴもまっきーに作ってもらいました!
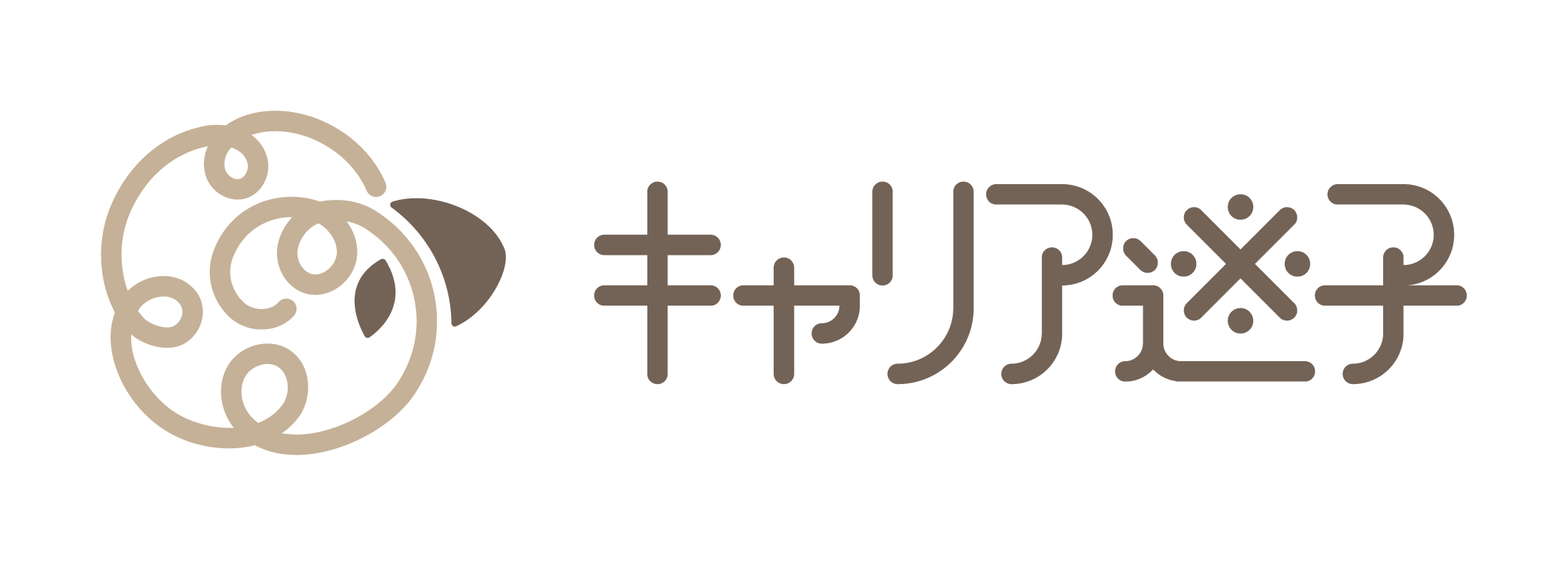
コメント